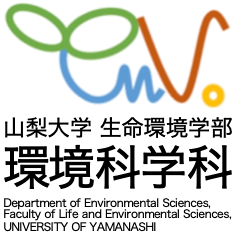環境科学がどのように社会に活かされるのでしょうか?今回はその事例を1つ紹介したいと思います!
環境科学と社会
「小さな水」技術による能登半島地震の復興支援
本学科の西田継教授をリーダーとする研究グループは、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム」(SOLVE for SDGs)の研究プロジェクト「小さな水サービスの導入を軸とした互助ネットワークの形成による、社会的効用創出モデルの開発と展開」において、小規模・分散型水サービス(水道、排水処理技術)の開発に取り組んできました。
また、令和6年1月に発生した能登半島地震により水インフラが甚大な被害を受けた石川県能登地方において、このプロジェクトで開発した技術を用いた復興支援活動にも取り組んでいます。これらの活動の様子は、各種メディアで紹介されています(下記はその一部です)。
・NHK NEWS WEB(2025.1.9)
「能登半島地震 生活用水確保に大学や民間企業による支援が効果」
詳しくはこちら
・NHKおはよう日本 (2025.1.9)
「能登半島地震1年 不足する生活用水 技術と工夫で確保」
・テレビ山梨(UTY) スゴろくニュース(2024.9.27)
「水害でやられたけど生活には水が必要」能登豪雨の被災地 山梨大学がモバイルろ過装置で支援
詳しくはこちら
・病院新聞 防災の日特集(2024.8.29)
「インタビュー・能登半島地震から考える水を寄せる試み」